信玄は直接浜松城(同)の家康は攻めず、合代島に陣を置いて勝頼に二俣城(同)を囲ませた。
十一月になると別働隊の秋山信友が美濃岩村城(岐阜県恵那市)を攻め、遠山景任夫人との再婚を条件に城を奪取するなど、じわじわと信長の勢力圏内に迫っていった。信玄は浅井長政と連絡を取りつつ、朝倉義景にも遠江出陣の近況と今後の作戦計画を報じている。信玄にとって、信長を破るには朝倉氏の兵力もまた必要不可欠なものであった。家康は信長に援軍を要請するが、兵力に余裕の無い信長は、佐久間信盛・滝川一益・平手汎秀らに三千の兵を付けて派遣したに過ぎなかった。
しかし十二月三日、何を考えたか北近江に進出していた朝倉義景が突然兵を退き、越前に帰ってしまったのである。この報に接した信玄は耳を疑い、事実とわかると茫然自失した。そして怒った。
「御手の衆、過半帰国の由、驚き入り候。おのおの兵を労ることは勿論に候。しかりといえども、此節信長滅亡の時刻到来のところ、ただ今寛宥の御備、労して功無く候か。御分別過ぐべからず候」
労して功無く候か・・・信玄の悲痛な叫びが聞こえるような文言である。この時点で信玄は、信長は自軍の力だけで倒すと決心したのかもしれない。この間、二俣城を囲んで水の手を断つことに成功していた勝頼は、十九日になって城を落とした。
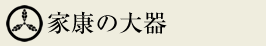
二十一日、家康は二俣方面に放っていた斥候から、信玄が明日東三河に進軍するとの報を受けると、諸将を集め軍議を行った。何と言っても敵は三万の大軍、味方はわずかに八千。老臣たちは当然出陣に反対するが、家康は聞かなかった。
「敵が我が領地を踏みにじって通るというのに、一矢も放たず見送るという法があろうか。勝敗は時の運、兵数が全てではない」
もちろん理由はこれだけではない。信玄と言えば戦国大名の中でも一、二を争う用兵術を持ち、しかもその兵は日本一と言われる程精強である。加えて「戦に勝つということは、五分を上とし、七分を中とし、十分を下とする」という持論を持っており、例え家康が数で少々上回る兵を率いて戦っても容易に勝てる相手ではないのである。
しかし家康には出撃せざるを得ない事情もあった。もし信玄が通過するのを指をくわえて見ていたならどうなるか。形ばかりとは言え援軍を送ってきた信長の信頼を損なうのみならず、信玄に内通したのではないかという疑いを掛けられる恐れもあった。家康はそれだけはどうしても避けたかったのである。
こうして家康は八千の兵を率いて浜松城を出陣した。一方の信玄は織田の援軍九隊が浜松に入り、なおも続々と詰めかけているという情報を入手したことから兵の消耗を避け、浜松城を北に迂回し三方ヶ原を経由して三河へ向かおうとした。武田勢が三方原に布陣したのを見た家康は自重を求める周囲の声も聞き入れず、ついに無謀とも言える戦いの幕が切って落とされたのである。
戦いは午後四時頃に始まり、激戦となったものの徳川方は惨敗、援軍の織田勢に至っては大半が一戦も交えず退却するという有様であった。家康もあわや討ち死にかという危機を迎えるが、その時浜松城の留守に残した夏目正吉が駆けつけ、家康の身代わりとなって壮絶な戦死を遂げたことにより九死に一生を得ている。
家康は大敗したが、その不屈の闘志は信玄のみならず、諸大名の家康評を大きく上げることとなった。この戦いは後に家康が飛躍する大きな下地となるが、それも生きながらえてこそのことである。
家康もまた、強運を持ち合わせた武将であった。
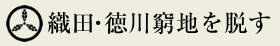
信玄は引き続いて軍を西へ進め、翌元亀四年正月三日、三河へ侵入して野田城(愛知県新城市)を包囲した。城内には菅沼定盈・松平忠正が籠もっており、家康は惨たる敗戦直後にもかかわらず、野田城を救援すべく出陣するが、武田の大軍に阻まれて手も足も出せない状態であった。
信玄は「信長包囲網」の要である足利義昭に書状を送り、戦況を報告した。その中で、「義景が再び出陣してくれたら」と朝倉氏の協力が必要なことを義昭にも述べている。信玄の進撃を頼もしく思った義昭は、再び信長に対して挙兵した。これが二月十三日のことである。義昭は近江園城寺の光浄院暹慶(山岡景友)らに檄を飛ばし、これに応じた彼らは一向宗徒を糾合して石山・堅田で籠城した。
信長はすぐさま柴田勝家・明智光秀・丹羽長秀らに討伐を命じ、二十九日にこれらを平定している。
本願寺顕如も朝倉義景に再出兵を依頼、義昭は三好三人衆・松永久秀と結び、京都所司代村井貞勝の屋敷を包囲する挙に出た。信長は三月二十五日に義昭攻撃のため京都へと軍を発し、四月四日には上京を焼き払って二条第を囲み、義昭を孤立させる。
中央でめまぐるしい攻防が起こる中、武田軍の進軍は三河野田城でぴたりと止まっていた。信玄は労咳(ろうがい=肺疾患)を患っており、これが悪化していたのである。 信玄は上洛を断念して帰国の途につくが、四月十二日に伊那駒場にてついに没した。信長は桶狭間・越前金ヶ崎に続き、またもや窮地を脱したのである。
二十八日、義昭は正親町天皇まで動かして信長と和睦するが、実質的には降伏である。しかしこの和睦はたちまち破れた。義昭は兵糧米の送付を毛利輝元に依頼し、七月になって今度は槙島城(京都府宇治市)に籠城したのである。信長はもはや義昭を許さなかった。七月十九日に槇島城を攻め義昭を河内に追放、ここに室町幕府は事実上滅亡し236年に及ぶ歴史の幕を閉じた。義昭は河内若江城(大阪府東大阪市)へ逃れ、のちに紀伊由良興国寺などを経て毛利領の備後鞆へと流れていくことになる。
浅井長政らの要請により越前一乗谷を出陣した朝倉義景は、八月十日になって北近江・地蔵山に着陣したが時すでに遅く、却って滅亡を早める結果となったのは皮肉である。信長は十三日、一旦退却して体勢を立て直そうとする朝倉勢に大規模な追撃戦を仕掛けた。朝倉勢は越前刀禰坂で追いつかれて惨敗、十五日に義景はかろうじて一乗谷に逃げ戻った。ちなみにこの戦いで、信長に美濃を追われて当時朝倉氏のもとに身を寄せていた斎藤龍興が戦死している。
もはや義景に従う者はほとんどおらず、義景はわずかの側近に守られて越前大野の東雲寺へと落ち延びた。しかし十九日に同族の景鏡から「東雲寺では防ぐに難しい」として六坊賢松寺へ移るよう勧められ、義景はその言葉に従って夕刻に六坊賢松寺に入るが、この頃信長軍の先鋒は一乗谷全域を炎と化していたのである。
翌日、六坊賢松寺は二百余騎の軍勢に包囲され鉄砲を撃ちかけられた。何と朝倉景鏡であった。もう逃げる場所のない義景はここに観念して自刃、四十一歳の生涯を閉じた。信長は直ちに軍を返し、二十六日に再び近江・虎御前山に戻った。
残るは浅井長政の小谷城である・・・。